北海道の中学校では、6月中旬から下旬にかけて1学期の定期テストが行われます。新学年が始まってまだ間もないこの時期ですが、中学1年生にとっては初めての定期テストとなり、中学2・3年生にとっても内申点や志望校合格に直結するため、軽視できません。この記事では、「定期テスト対策はいつから始めればいいのか」という疑問に答えながら、具体的な勉強法や教科別の対策方法を詳しく紹介していきます。
1. 定期テスト対策はいつから始めるべき?
一般的に、定期テストの2週間前に学校から範囲が配布されるので、そこから本格的な対策を始めるのが理想的とされています。しかし、これは「テスト勉強」という意味であって、準備そのものはもっと早くから始まっています。最も大切なのは、「授業を日々しっかり理解しておくこと」。これがベースになって初めて、2週間前の勉強が効果を発揮します。
……では実際に、どういう取り組みが理想なのか。時系列順に下記にまとめてみました。
より詳しい取り組み内容は、更にクリックをしてみて下さい!
【目安スケジュール】 例:1学期末テスト
・各教科の進度を確認し、これまでに学習した範囲を得意・苦手に分類する。
・テスト範囲を予測しながら、復習に必要な教材(ワーク・ノート・プリントなど)を準備する。
・学校ワークを全体的に1周解き、間違えた問題に印をつけておく。
・授業ノートや教科書を読み返し、理解不足の単元を重点的に復習する。
・学校ワークの2周目に取り組み、1周目で間違えた問題を中心に繰り返し演習する。
・不明点はそのままにせず、学校や塾の先生に早めに質問して解決する。
・ワークの応用問題、教科書の章末問題、塾のプリントなどを活用して実践力を高める勉強を行う。
・過去の定期テスト問題や類題を解いて、出題パターンに慣れる。
・ミスノートに記録した間違いや弱点を重点的に復習し、苦手を克服する時間に充てる。
・覚えきれていない暗記項目(理科・社会・英単語・漢字など)を短時間で繰り返しチェック。
・1日1教科ずつ総復習する形が効果的。
テスト範囲が配られるよりも前から、定期テストの対策はスタートしています!学校で習った単元は、すぐに復習することから始めていきましょう!
2. 定期テストで高得点を取るべき理由
中学生にとって、定期テストは避けて通れない関門です。しかし、単なる通過点として軽く見てしまっていないでしょうか。 特に北海道の高校入試では、定期テストの点数=内申点に直結します。
つまり、「定期テストで高得点を取ること」は、高校受験の合否に直接関わる最も重要な要素なのです。
そして、この目標に向かってしっかり努力する過程では、「プラスアルファの効果」も得られます。ここでは、まず本命の理由としての“内申点アップ”を押さえたうえで、その努力の中で得られるメリットも紹介します。
高得点が「内申点」を握る
定期テストの点数は、通知表の評定(1〜5)の大部分を決めます。北海道の公立高校入試では、以下のように内申点が合否に大きく影響します。
- 評定アップ
定期テストの得点は通知表の評定に直結し、評定が上がることで内申点も高くなります。 - 安全圏を確保
北海道の多くの高校入試は「内申点+当日のテスト点」で合否を判定します。内申点が高ければ、当日点で多少ミスしても合格圏を維持できます。 - 推薦・特待制度の条件クリア
一部高校では「評定平均○以上」「○ランク以上」などを出願条件に設定。高得点を取り、内申点を上げることで、推薦入試の選択肢が広がり、特待制度を受けられる可能性も高くなります。
このように、定期テストの高得点は受験戦略の要(かなめ)です。
さらに、内申点を上げるために計画的に勉強に取り組む過程で、自然と以下の力が身につきます。テストで高得点を取ることは、頑張ったことが結果として返ってくる経験にもなります。
プラスアルファの効果
●勉強の習慣が身につく
定期テストに向けて計画的に学習することで、「やるべきことを整理して進める力」や「自分の理解度を把握する力」が養われます。これは高校受験にとどまらず、その後の学習や社会生活にも役立つスキルです。
●自信につながる
努力の成果が点数として現れることで、生徒自身の「やればできる」という成功体験につながります。このポジティブなサイクルが、次の学習にも良い影響を与えます。
そして、この高得点を取るためには、先述した準備が必要になります。高得点を取ることは、テスト勉強のスタート時期と密接に関係しています!
3. やっておくべき事前準備
では、早めにテスト勉強を始めれば点数は上がるのでしょうか……ただ闇雲に勉強を始めてしまうと、何から手をつけていいかがわからなくなります。
そのため、早めに勉強を始めるときは、その分事前準備が必要になります。
●教科書・ワーク・ノートの整理
まずは授業で使っている教科書やノート、学校のワークを見直し、どの範囲がテストに出るのかを把握します。ページの抜けやノートの取りこぼしがないか確認しましょう。
●テスト範囲表の確認
テスト2週間前になると配布される「テスト範囲表」は超重要資料です。どの単元が出るのか、提出物は何か、ワークの範囲はどこまでかなど、しっかりチェックしましょう。
●スケジュール作成
テスト4週間前には、1日ごとの学習スケジュールを作成するのが理想です。「復習→問題演習→見直し」のサイクルを2回転できるくらいの計画がベストです。
授業を受けた単元からノート整理、サイクルを2周できるよう計画を立て、テスト範囲表を確認して取り組むべき内容を確認する。しっかりと癖付けをしていきましょう!
4. 効果的な勉強法
事前準備の後は、勉強スタートです! 実際にどのようなところに意識すべきでしょう。
どの教科を勉強するとしても共通する内容を、簡単にまとめてみました!
●インプットとアウトプットのバランス
ただ教科書を読むだけではなく、問題を解いてアウトプットすることが理解の定着に繋がります。「覚える→使う→確認する」のステップを繰り返しましょう。
●自分の弱点を知る
間違えた問題や、理解があいまいな単元は「ミスノート」にまとめましょう。自分専用の復習ノートを作ることで、効率よく弱点補強ができます。
●塾の動画を活用する
「問題を解いて間違えたとき」や「ノートや教科書を読んでも理解できなかったとき」は、当塾の動画を見直して理解を深めましょう!
授業中に聞き逃した部分や、イメージがつかみにくかった実験・図解の単元なども、動画なら繰り返し視聴できるので「自分のペースでわかるまで勉強する」習慣がつきます。
では各教科ではどうなのか。各教科にまで絞ったうえで、取り組みを考えていきましょう!
主要五教科それぞれで、対策の方法が違います。どのように対策を立てていくか。下記にまとめてみました!
主要五教科の勉強法指南
文法や漢字の確認
・テスト範囲の文法用語(助詞・接続詞・敬語など)を教科書・プリントで確認。問題集で基本問題を3回繰り返す。
・漢字練習は1日10個×3日で30個を覚えるペースがおすすめ。読み・書き・意味をセットで確認。
記述問題の対策
・授業で使ったノートやプリント、模範解答を読み直し、どんな書き方をすると点が取れるのか分析する。
・「なぜそう思うか」と聞かれたときの答え方パターンを練習しておく。
計算ミスを防ぐための繰り返し練習
・ワークの計算問題を最低2周は解く。特にミスした問題はチェックを入れて、次の日に「もう一度だけ」解き直す習慣をつける。
文章題の解法パターンを覚える
・「割合」「速さ」「一次方程式」など、単元ごとに公式と使い方をノートにまとめる。
・例題を真似して、「この言葉が出たらこの式」と対応できるように解き方の型を覚える。
単元ごとの公式を暗記し、使えるようにする
・「公式は覚えているけど使えない」状態を避けるため、公式を使った応用問題に毎日1〜2問取り組む。
地理・歴史の流れを理解する
・地理:地域の特徴、気候、産業の流れを図や地図を見ながら理解する。白地図を使って場所の確認も行う。
・歴史:時代の順番や出来事の前後関係を、年表や因果関係(原因→結果)で整理する。
重要語句の暗記+意味まで理解
・ワークや教科書の太字をピックアップし、赤シートや暗記カードで繰り返し確認。
資料の読み取り問題に慣れる
・グラフ・表・写真などが使われた問題を、ワークや過去問で実際に解いてみる。
用語の暗記(図や表とセットで覚える)
・「光合成」「電流」「状態変化」などの用語を、図や実験器具のイラストと一緒に覚える。
実験の手順や結果の理解
・テスト範囲の実験の「目的」「使った道具」「結果」について、プリントや教科書の図を見ながら説明できるようにする。
計算問題(電流や密度など)の反復練習
・1問解いたら答え合わせをし、「なぜ間違えたか」を確認し再挑戦する。
教科書本文の確認と和訳
・1文ごとに和訳できるかチェックし、わからない単語や文法には印をつける。
・英語が苦手な人は、日本語→英語の順で音読練習をして定着させる。
・テスト範囲の単語を1日10語ずつ覚えていく(英単語→意味→例文の流れで)。
文法問題のパターン練習
・「be動詞と一般動詞の違い」「三単現のs」「過去形」など、文法項目ごとにミニテストをする。
以上、定期テスト対策を始める時期についてお話をさせていただきました!
定期テスト対策は、4週間前から始めるのが理想です。しっかりとスケジュールを立てて、計画的に学習を進めれば、誰でも確実に成績アップが狙えます。特に北海道の高校入試では内申点が重視されるため、1回1回のテストがとても重要です。中学生のみなさんは、ぜひ今回のテストから意識を変えて、しっかり準備して臨みましょう!
【お問い合わせ・無料体験授業のお申込み】
TEL: 0144-82-8011
公式LINEでのお問い合わせも大歓迎です!


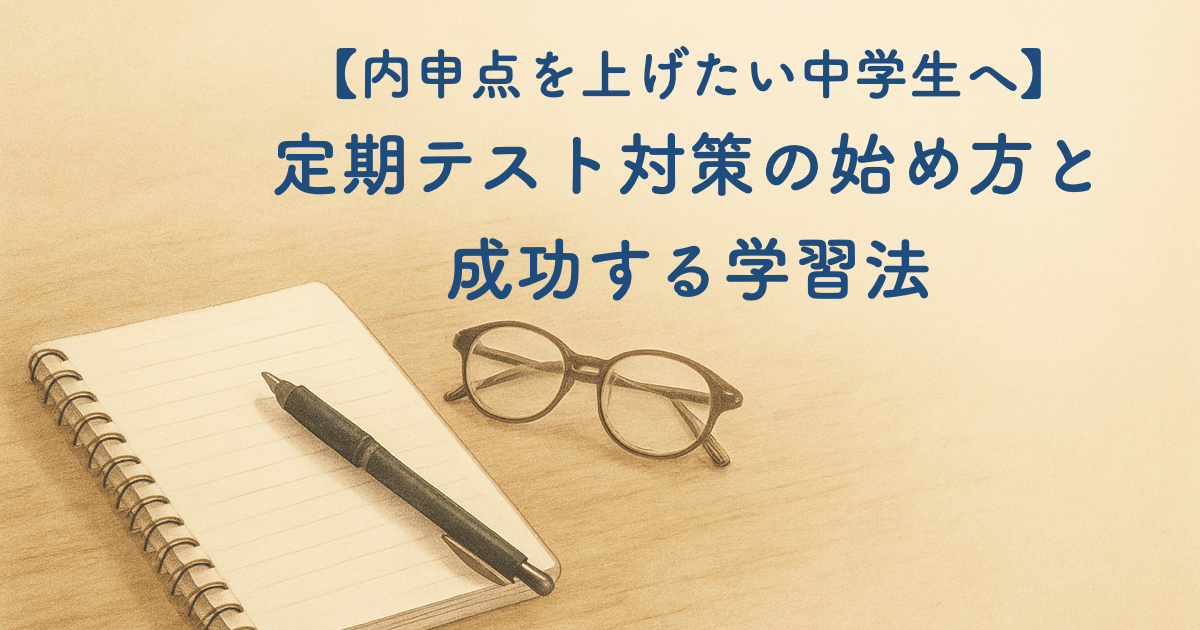
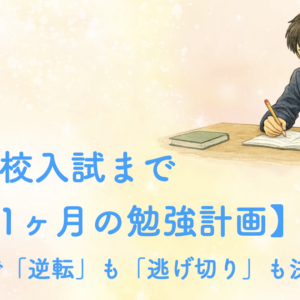
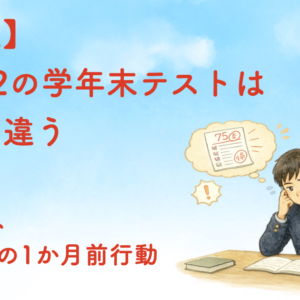
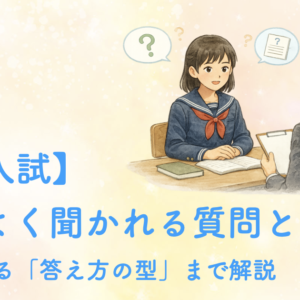
コメント