「なかなか覚えられない」「頑張ってもすぐ忘れてしまう」——そんな悩みは、誰にでもあります。
でも安心してください。記憶には“科学的に効果のある覚え方”があります。この記事では、中学生・高校生とその保護者の方に向けて、学校や家庭ですぐに実践できる「暗記のコツ」を紹介します。勉強がもっと楽しく、そして自信につながるヒントを、わかりやすくまとめました。
目次
1. 思い出して、間違えてこそ伸びる
― “想起練習”と“エラー学習”のススメ ―
ただノートを眺めたり、教科書を写すだけの勉強になっていませんか?
実は「自分で思い出そうとする」ことが、記憶を強くする一番の近道です。
この“想起練習”は、脳科学でも「本当に身につく暗記法」として効果が証明されています。
また、思い出そうとして間違えても大丈夫。
「どこが違ったのか」を確認し直すことで、記憶はより確かになります。
保護者の方も、間違いを責めるのではなく、「チャレンジしたことが大事!」と声をかけてあげましょう。
親子でできる例
- 教科書を閉じてクイズにして出し合う
- 問題集を解いたあと、間違えたところを一緒に振り返る
- 「今日は何を覚えた?」と話す時間をつくる
2. “時間を味方に”――間隔を空けて復習しよう
―「忘れるメカニズム」を活かした、賢い学び方 ―
まとめて一気に暗記する「一夜漬け」では、テスト後にすぐ忘れてしまいがちです。
何日か空けて繰り返す「間隔復習(分散学習)」によって、記憶は長持ちします。
忘れかけた頃にもう一度テストしてみると、脳が「これは大切な情報だ」と認識し、よりしっかり記憶に定着します。
保護者の方も、「復習の日」をスケジュールに入れるなど、声かけとサポートを意識すると効果的です。
おすすめ実践例
- 単語を、翌日・3日後・1週間後にクイズ形式で復習
- スマホやカレンダーに「復習日」の予定を入れる
- 「1日1分でもいいから毎日復習」を習慣にする
3. 意味づけ&イメージ化で“引っかかり”を作る
― ストーリーや図解で記憶力アップ ―
丸暗記よりも、「意味」や「イメージ」を加えることで記憶に残りやすくなります。
歴史の年号はストーリーにしたり、理科や数学の用語は図解や関連図で覚えたり、自分なりの方法で「関連づける」のがポイントです。
保護者の方も、「どうやって覚えたの?」「どんなふうに説明できる?」と問いかけることで、理解と記憶が深まります。
具体例
- 語呂合わせやおぼえ歌で楽しく暗記
- ノートに図やイラストを描いて整理
- 物語のように、歴史の流れをストーリーで覚える
- 習ったことを誰かに説明してアウトプット
まとめ|NGな暗記法と、保護者からのひと声
「ノートを写すだけ」や「長時間続けるだけ」の勉強法では、記憶は定着しにくいものです。大切なのは、小さな工夫や挑戦を積み重ねること。保護者の「よく頑張ったね」という前向きな声かけが、子どものやる気を引き出します。
ほんの少し“やり方”を変えるだけで、暗記の力は着実に伸ばせます。今日から試してみましょう!
▼もっと詳しく知りたい方はこちら:
脳科学に基づく暗記のコツ!学生が知っておくべき8つのテクニック(代々木ゼミナール大阪南校コラム)
よくある質問(FAQ)
-
なかなか覚えられないとき、どうすればよいですか?
-
無理に何度も繰り返すより、いったん間を空けて復習するのが効果的です。
忘れかけたタイミングで思い出すと記憶に残りやすくなります。
語呂合わせやイメージなど、自分なりの“引っかかり”を作る工夫も試してみましょう。
-
テスト直前はどう勉強するのが効果的ですか?
-
教科書を読むだけでなく、クイズを作って解いたり、声に出して説明したりといった「想起練習」が有効です。
短時間でも苦手な部分を繰り返すことが、得点力アップのカギです。
-
保護者が家でできるサポートは?
-
一緒にクイズを出し合ったり、「今日はどんなことを覚えたの?」と質問して説明してもらうだけでも十分なサポートになります。
努力の過程や工夫を認める声かけが、子どものやる気を引き出します。
-
語呂合わせやイメージ化が苦手な場合の対策は?
-
無理に語呂合わせを作らなくても大丈夫です。
図や表を書き写したり、カラーペンで工夫したり、誰かに説明することで記憶の助けになります。
-
一夜漬けや長時間勉強のデメリットは?
-
一夜漬けや長時間の詰め込みは、一時的には覚えられても長期記憶には残りにくいです。
数日おきの復習やこまめなテストのほうが、結果的に効率よく覚えられます。
【お問い合わせ・無料体験授業のお申込み】
TEL: 0144-82-8011
公式LINEでのお問い合わせも大歓迎です!


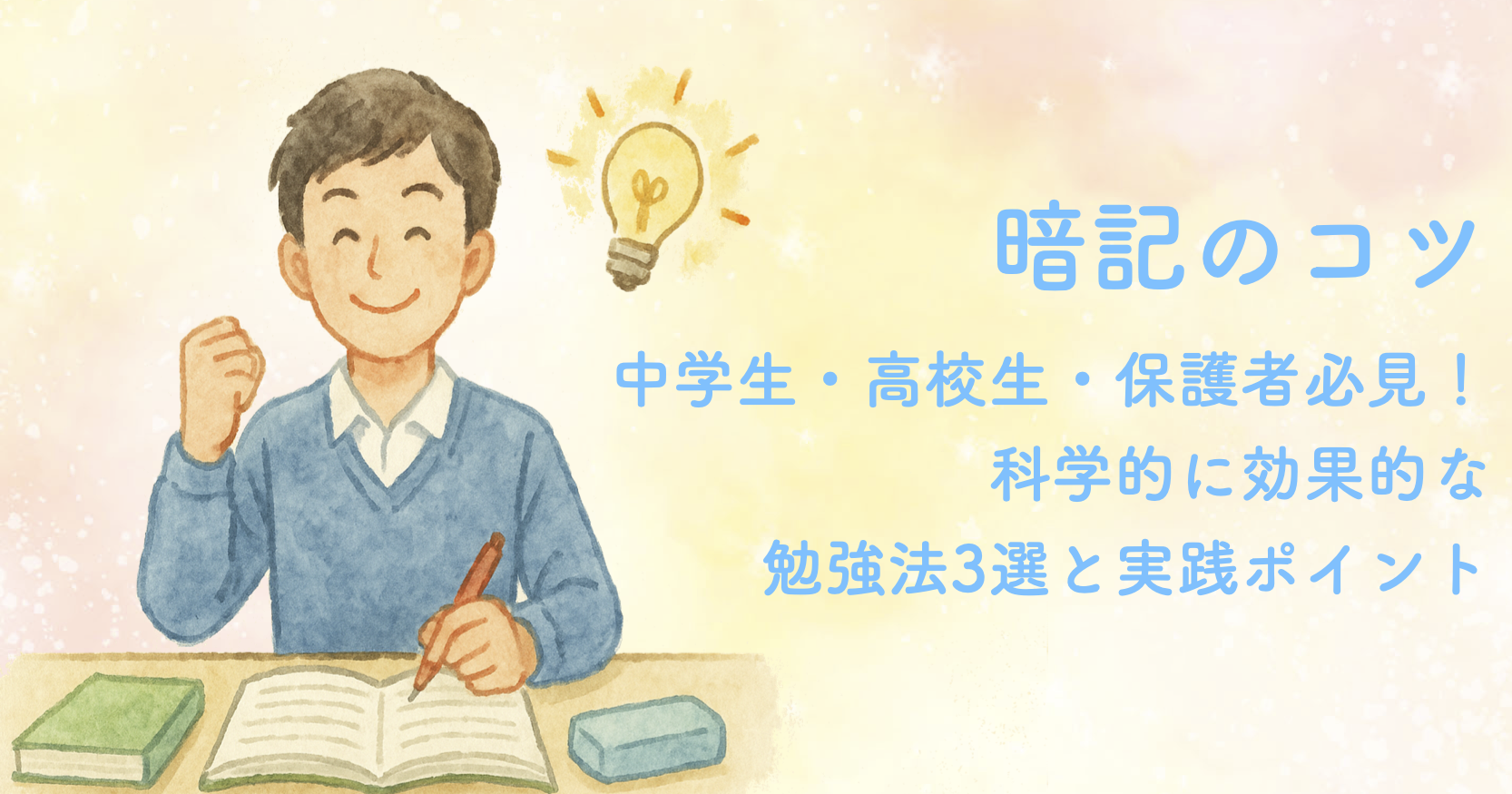
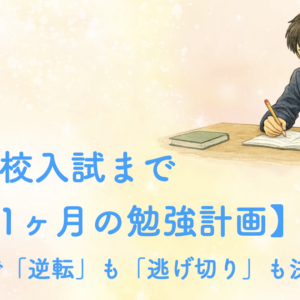
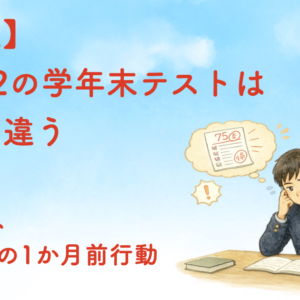
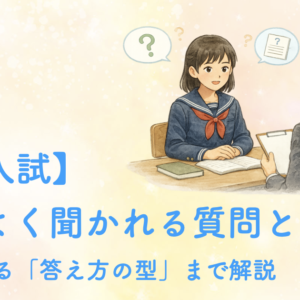
コメント