「数学が苦手…」と感じている中学生はとても多く、保護者の方も「うちの子は大丈夫かな」と心配になることが多いでしょう。
しかし数学は、適切な勉強法と継続によって必ず克服できる科目です。
実際に塾の現場で、数学で平均点に届かず苦戦していた生徒が、適切な勉強法を実践することで2か月後には「平均点+20点」を取れるようになった例もあります。
この記事では、数学が苦手になる原因を整理し、2か月で変わるための具体的な克服ステップを紹介します。
苦手を「できる!」に変えるきっかけにしてみてください。
この記事でわかること
- 数学が苦手になる主な原因を具体的に理解できる
- 「基礎にさかのぼり」「理解を重視した演習」「繰り返し学習」など効果的な対策法がわかる
- 前向きな学習習慣をつくるための具体的な心構えと励ましを得られる
- よくある質問Q&Aで「つまずきあるある」への対応方法が確認できる
なぜ数学が苦手になるのか
中学に入ると、文字式・方程式・関数など、日常生活と結びつきにくい抽象的な内容が一気に増えます。
イメージができず「なんのためにやるの?」と感じてしまい、苦手意識につながります。
例えば比例や一次関数のグラフを「速さや料金の変化」といった身近な場面に結びつけられるかどうかで、理解のしやすさは大きく変わります。
数学は「積み上げ型」の科目です。
中1の正負の数があやふやだと、方程式もグラフも理解できません。
過去の理解不足がそのまま次の単元のつまずきになります。
実際、計算ドリルの復習を2週間続けただけで「二次方程式が分かるようになった」という生徒もいます。
基礎の積み上げがどれだけ大切かを実感できます。
「授業についていけない」という経験が続くと、自信をなくし「自分は数学ができない」と思い込んでしまいます。
集中力が続かない、勉強が習慣化していないことも苦手の大きな要因です。
集中力や学習の持続に課題がある場合は、特にスケジュール管理や学習環境の工夫が必要です。
例えば「25分集中→5分休憩」のポモドーロ法を取り入れると、集中が持続しやすくなります。
ポモドーロ法について、詳しくはこちら
「この公式を覚えれば解ける」という丸暗記は、一見便利ですが応用が効きません。
「なぜこの公式が成り立つのか」「どんな場面で使うのか」を理解していないと、少し問題が変わるだけで太刀打ちできなくなります。
実際、テスト本番で「見たことがない問題」が出ても、本質を理解していれば落ち着いて対応できるのです。
2か月で変わる克服ステップ
- ステップ1:基礎に戻る・本質の理解
- つまずいた単元までさかのぼり、教科書や基礎問題集で理解を確認します。
小学校内容まで戻っても構いません。
「なぜそうなるのか」を言葉で説明できるレベルを目指しましょう。
例えば「正負の数の計算ルール」を図や具体的な例で整理できるようになると、自信がつきます。
- ステップ2:反復学習と間違い直し
- 人は忘れる生き物です。1か月で同じ問題を3~7周解く意識を持ちましょう。
間違えた問題は必ず印をつけ、原因を分析し、再度自力で解けるまで繰り返してください。
自分だけの「間違いノート」を作るのも効果的です。
- ステップ3:予習と複数教材での理解
- 授業に置いていかれないために、簡単に予習しておくのがおすすめです。
また、学校の先生以外の解説(塾、参考書、YouTube)に触れると「なるほど!」と理解が進むことがあります。
例えば「解説動画で見た説明」と「教科書の説明」を比べると、違う角度から理解が深まることがよくあります。
- ステップ4:環境と声かけ
保護者の方は「なんでできないの?」ではなく「難しいよね、でも一緒に考えよう」と共感を示してあげてください。
例えば「今日はここまでできたね!」と進歩を認める声かけが効果的です。
塾や家庭教師など外部の力を借りるのも有効です。
なぜ数学をやらなければならないのか
「なぜ数学を勉強しなければならないのか?」と疑問に思う人は多いでしょう。
たしかに、日常生活で連立方程式や因数分解をそのまま使うことはあまりありません。
けれども勉強の本当の目的は、知識を直接使うことよりも、問題に向き合い、自分で考え、試行錯誤し、結論を出す力を鍛えることにあります。
数学はまさにその練習にぴったりの科目です。
筋道を立てて考える力や問題を解決する力を育ててくれるだけでなく、困難に挑戦する粘り強さも身につけられます。
例えば買い物で値引き後の金額を計算したり、ニュースに出てくるデータを正しく読み取ったりするのも数学で鍛えた力が生きている場面です。
さらに、部活動で友達と協力して試合の作戦を考えるときや、文化祭の準備でどうすれば効率よく作業できるかを相談するときも同じです。
実際に生活の中で『どうすれば一番うまくいくか』を考える場面では、数学で身につけた考え方が自然と役立っています。
数学を学ぶことは、ただ点数を上げるためだけでなく、「生きる力」を磨き、自分の可能性を大きく広げる挑戦なのです。
よくある質問Q&A
-
公式を丸暗記してもいいですか?
-
単に公式を暗記するだけでは応用できません。
「なぜ成り立つのか」まで理解してから覚えることが大切です。
例えば、ひし形の面積公式は、外側に接する大きな長方形を半分にした形だと考えると説明できます。
このように公式の成り立ちを理解すると、丸暗記ではなく納得して覚えられるので、少し形の違う問題にも落ち着いて取り組めるようになります。
-
テストになると途中で集中が切れてしまいます。どうすれば?
-
簡単な問題から解いてリズムをつくる、時間配分を意識することで集中を保ちやすくなります。
普段の勉強でも「この問題は10分で解く」といったように時間を区切る習慣を持つと、テスト本番でも集中力を維持しやすくなります。
学校ワークや過去のプリントを使って「25分計測で大問1~3まで解く」といった練習も効果的です。
-
数学への苦手意識がどうしても消えません。
-
「自分はできない」ではなく「まだ学んでいないだけ」と考えてみましょう。
この気持ちの切り替えが、苦手克服の第一歩です。
そして何よりも大切なのは、小さな成功を積み重ねることです。
例えば「昨日できなかった問題が今日できた!」という経験を重ねるたびに、自分の成長を実感できます。
その積み重ねがやがて大きな自信となり、数学への苦手意識を乗り越える力になります。
-
計算ミスが多くて点数を落としてしまいます。どうすれば?
-
計算ミスは、例えば「性格の問題」などではなく、「気をつける」といった精神論ではなかなか改善しません。
具体的な工夫が必要です。
途中式を必ず書く、答えを出したあとに検算して確認する、見直しの時間を必ず5分以上確保するなど、行動に落とし込んだ習慣を持つことが大切です。
特に同じミスをしたら必ずノートにまとめ、自分の「弱点パターン集」をつくっておくと、次に同じ間違いを防げます。
-
家で勉強する習慣が続きません。
-
いきなり1時間机に向かうのではなく、まずは5分からでも構いません。
短い時間でも毎日続けることで「勉強するのが当たり前」という感覚が身につきます。
保護者の方は、できたときに「よく頑張ったね」と声をかけてあげることが大切です。
ちょっとした言葉が子どものやる気を大きく後押しします。
まとめ
数学は、適切な学習の継続によって「苦手が得意に変わる」科目です。
原因を理解し、基礎から少しずつ積み上げ、2か月間継続することで必ず成果が見えてきます。
授業の中で「できた!」と声を上げる瞬間、子どもの笑顔から大きな自信が芽生えていることを強く感じます。
以前、分数が全くできなかった生徒が、毎日15分の学習を2か月間毎日続けた結果、テストで合格点を大きく超える点数を取って来てくれました。
そのときの喜びは本人や家族、そして私たちにとっても、大きな達成感として心に残る出来事となりました。
適切な方法・適切な量の学習を継続していけば、あなたにも、必ずその瞬間が訪れます。
【お問い合わせ・無料体験授業のお申込み】
TEL: 0144-82-8011
公式LINEでのお問い合わせも大歓迎です!


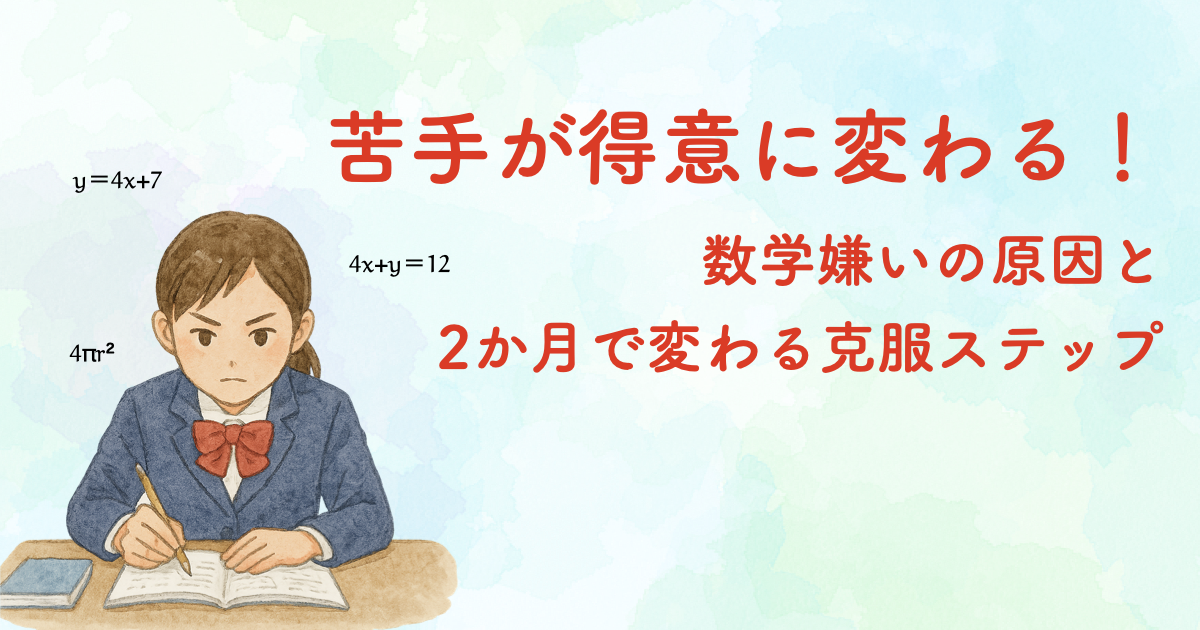
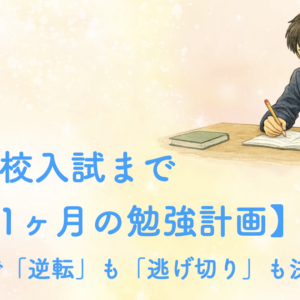
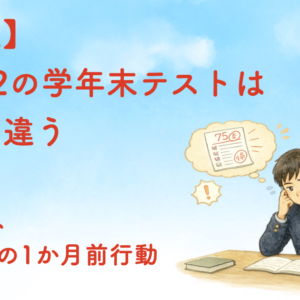
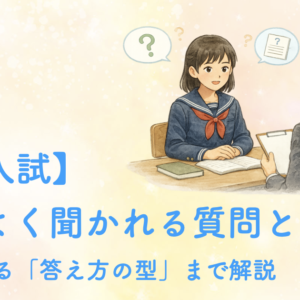
コメント