今回のテーマは『部活と勉強の両立!』
平日は授業後に部活やクラブ活動、週末も朝から夕方まで練習に励む――。そんな多忙な毎日を送る生徒にとって、「勉強との両立」は一見難題に見えるかもしれません。
が、結果を出さなければならないテストは決まった日程でやってきます。
まずは次のテストのそれぞれの教科で何点をとらなければならないのかの目標の設定と、その目標に向けて実際に学習に取り組んでいくためのマインドセットについて考えましょう。
①目標設定について
まずはゴールを設定しないと、ペース配分がわからないまま勉強をすることになります。そのため、志望校によって目標を設定していきましょう!
たとえば、「苫小牧東高校」や「苫小牧高専」を目指す生徒の場合、次の2つの目標を意識してみましょう。
苫小牧東高校・苫小牧高専を目指すための目標例
1,定期テストでは、主要5教科で少なくとも合計400点を目標に
1教科あたりは80点ベース。つまりは苦手教科でも難しい問題(4〜5点配点の問題)を4問ほど間違えてしまってもクリアできる設定になります。
自分の実力をはかる目安をお伝えすると、テスト範囲の学校ワークを完璧にこなせる状態(教科書などを見なくても自力で解ける)になっていれば、80点は確実に狙える実力がついているはずです。
※この時は、解答するのに悩んだ問題や当てずっぽうで正解した問題があればそれは×として考えてください。
2,内申点はBランクを最低条件に設定
今の時代は内申点のインフレが起きています。苫小牧東高の合格者平均の内申点はBランクです。
Bランクがないと合格できないわけではありませんが、通知表の評定は、定期テストや小テストなどの成績が大きく影響します。Bランクを取るには、十分な学力と日々の学習量が求められると考えてください。
また、中学2、3年生は過年度の評定がすでにありますので、それらを基準に「この教科の評定を4から5に上げよう!」などと、より具体的に各教科の目標を立てていくとより良いですね。
目標点について、その他の高校はどうでしょうか。
その他苫小牧南高であれば350点、苫小牧西高や苫工業上位学科(電子・電気・情報)では300点、苫工業のその他学科や苫総経は250点を目安に設定しましょう。
②マインドセットについて
次はマインドセット。勉強をするにあたって、心構えは大事なことです。
部活が終わったあと、疲れた体で勉強しなければいけないこともあります。
だからこその心構え。勉強に向かうためにどんな意識をしていくべきか、3つほどお話していきましょう。
勉強に取り組むためのマインドセット
1,まずは10分間でいいので勉強をやり始めること!
人間の脳は何かしらの作業を始めるとアセチルコリン(神経伝達物質)を分泌し始めます。アセチルコリンの分泌によってやる気が高まり、集中力がアップします。この状態を「作業興奮」と呼びます。
この作業興奮は作業始めから5〜10分ほどで起きるとされています。
そのため、まずは10分間でいいので「勉強をやり始める」という癖付けをしていきましょう!
2,簡単な暗記問題などから始め、10〜20問程度を覚えたら小テストをしよう!
「小テストを行う」これがとても大切です。
その程度の問題数でテストをやって意味があるの?と思われるかもしれませんが、ここでのポイントは2点あります。
まずは記憶するのに効果的な方法であるということ。記憶は反復作業や思い出しの作業で強化されると言われており、またこれらの作業は記憶したい物事を短期記憶から長期記憶に移行する方法の1つとして知られています。
続いて、小テストで「できた!」を実感すると脳内の報酬系の神経伝達物質であるドーパミン(別名:幸せホルモン)が分泌されます。このドーパミンは快楽や幸福感をもたらし、意欲や動機付けに関与し、目標達成を促してくれるとされています。
細かい小テストが重要です。暗記問題は「10〜20問程度を暗記したら」覚えているかどうかの小テストをしてみましょう!
3,スマホはできるだけ離れた位置に置こう!
自室で勉強するならスマホはリビングに置いておくなどの工夫をお勧めします。
近年増加しているスマホ依存。マナーモードや通知OFF設定にしていても、スマホが視界に入るだけでも、集中力が低下すると言われています。
また、特にSNSなどは脳を疲労させ、集中力や記憶力を低下させると言われています。テスト前などは必要最低限に利用を控えるか利用の一時中止をお勧めします。
音楽を聴きながらやりたい人もいると思いますが、一般的にはあまり良いとはされていません。特に歌詞がある好きなアーティストの歌などは、脳がそちら側に使われてしまい勉強に非効率になるなどのデメリットが発生する場合があります。ただし、それでモチベーションが上がり、勉強に取り組めるのであれば、上手に活用するのも一つの手です。
音楽を聴くのであれば、歌詞の無いクラシックや作業用BGMなどを控えめな音量で流すことをお勧めします。
③時間の使い方
さて、目標設定、マインドセットも大丈夫……となったときに、問題になるのが時間の配分ですよね。
新たに時間を作り出すことはできません。1日は24時間であり、テストまでの残り日数も決まっています。
ではどうやって時間を作り出すべきでしょう。部活との両立を考えると、帰宅後の時間で作り出すしかありません!
テストで結果を出すという目標を達成するために、以下の2つに注目をしてみましょう!
時間の作り方
1,「やらなくてもいいこと」に注目しよう!
例えば、SNSや友達とのメッセージのやりとり、動画を見る時間はどうでしょうか。
スマホが近くにあると、上記の内容で時間が奪われがちです。お分かりの通り、これらの時間をできるだけ短縮しなければ、新たな勉強時間を確保するのは難しいでしょう。
ここはしっかりと自立して目標の達成のためにマインドセットしてください。
2,目標から必要な時間を逆算していこう!
遅くともテスト1ヶ月前には各教科の学校ワークなどの取り組まなければいけないページ数を割り出し、テストまでの残り日数で日割りし、1日あたりどれほどの量を取り組むべきかスケジュールを算出しましょう。
ギリギリになってから確認しても、計画時点で時間が足りない! ということになります。余裕があるときに計画を始めましょう!
自分の進みたい高校や進路によりますが、上の目標設定でお伝えした通り、すべてのことを完璧にする必要はありません。スケジュール通りに進まないこともありますので、目標に応じて重点教科を調整したり、教科内でも基礎問題に絞って取り組んだりと、工夫をしながら進めましょう。
④時間帯別、おすすめの勉強法
最後に、時間帯別のおすすめ勉強法をお伝えします。
あくまで「効果的だとされる」方法であり、必ずしも従う必要はありません。
もし1日中勉強できる日があるとしたら、是非参考にしてみていただければと思います。
いつ、何を勉強するか
朝:集中力と思考力を必要とする勉強(難解な問題、レポート作成など)、暗記した単語の復習や確認テスト、音読など
昼:眠気が出にくい時間帯にメリハリをつけて短期集中で勉強を進める(問題演習、理解を深める勉強など)、休憩を挟む
夕方:休憩を挟んで、集中力を高める勉強(問題演習、理解を深める勉強など)、夕食前に、お腹が空いている時間帯に勉強する
夜:暗記や単語のインプット、シャドーイング、就寝前に勉強、集中力が高い時間帯に集中して勉強(21時~23時)
部活動と勉強の両立のためには時間の管理が必要……ですが、必要な時間は目標にする点数や内申点により変わり、その目標は志望校によって大きく変動します。
後回しにすればするほど、残っていた時間は少なくなっていきます。思い立ったが吉日、さっそく時間の配分を考えていきましょう!
【お問い合わせ・無料体験授業のお申込み】
TEL: 0144-82-8011
公式LINEでのお問い合わせも大歓迎です!


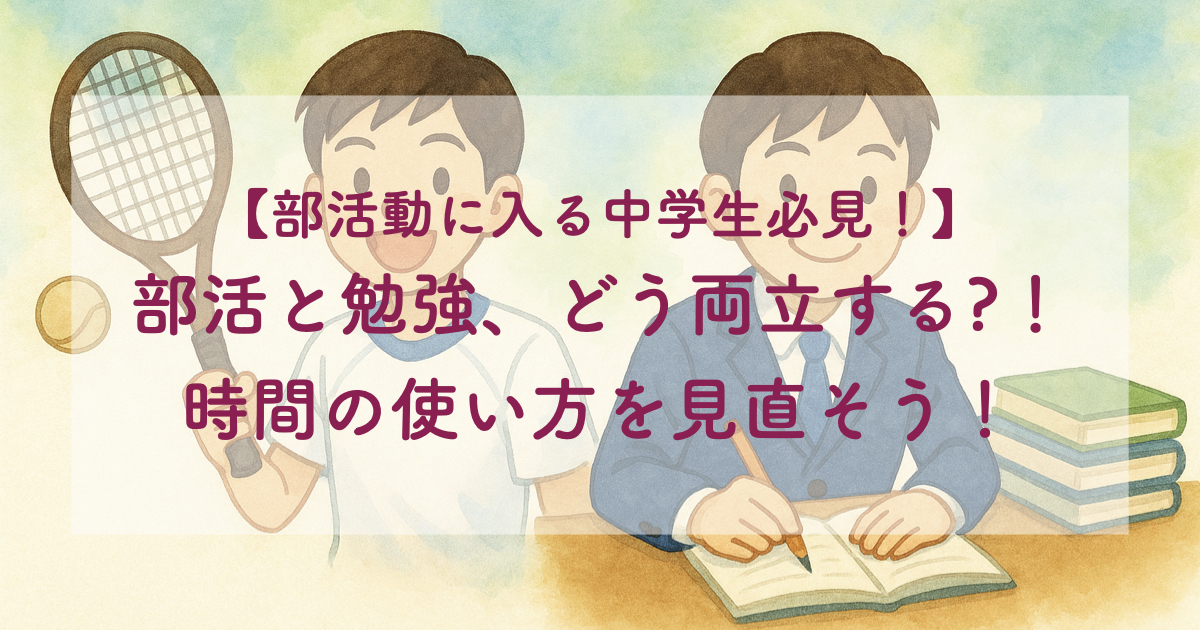
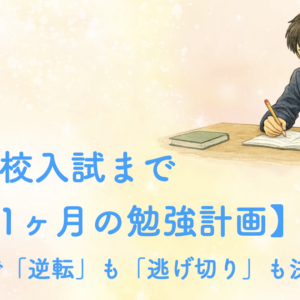
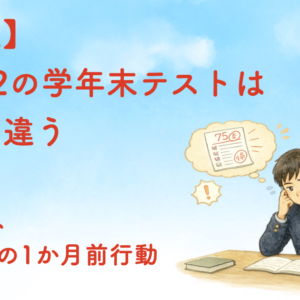
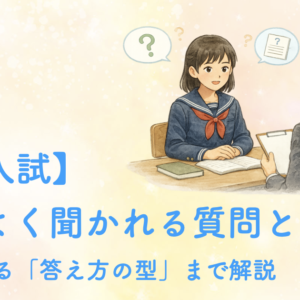
コメント