現代の中学生にとって、スマートフォンは生活の一部となっています。しかし、その使い方によっては、学力や脳の発達に大きな影響を及ぼすことが分かってきました。この記事では、文部科学省のデータや脳科学の知見をもとに、「スマホとの適切な付き合い方」について考えていきます。
スマホの使用時間と学力の関係
東北大学と仙台市が行った7万人規模の調査によると、スマホの使用時間と学力には明確な相関関係があることが分かっています。
まずは下のグラフをご覧ください。

(出典元 https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101101/)
このグラフは、東北大学が小学5年生から中学3年生の約4万人を対象に調査した結果を示したものです。スマホの使用時間が長ければ長いほど、テストの結果が良くないことが一目でわかります(インターネットに接続できる機器全般についてのアンケートですが、大半がスマホ利用のため「スマホ」と表記しています)。
しかし、「スマホの使用時間が長い生徒の勉強時間が短い」ことが原因なのか、「スマホの使用によって睡眠時間が短くなっているのでは?」といった影響を、このグラフからだけでは読み取ることができません。
続いて、3つのグラフを見てみましょう。



(出典元 https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101101/)
これらのグラフは、横軸が勉強時間、縦軸が睡眠時間、高さがテストの成績を表しています。グラフは上から順に、「スマホ使用が1時間未満」「スマホ使用が2~3時間」「スマホ使用が3時間以上」の生徒を表しています。また、黒色の棒は偏差値50(その模試の平均点)を超えていることを示しています。
スマホの使用時間が長くなるほどテストの成績が悪いことは、先ほどのグラフと同様に読み取れますが、その中でも注目していただきたい点は、次の2つです。
- スマホを3時間以上使用する生徒では、平均点を超える生徒がいない
- 睡眠時間が同じ「7~8時間」でも、スマホの使用時間が短く勉強をほぼしていない(30分未満)生徒が平均点を超えているのに対し、スマホを3時間以上使用し、勉強も3時間以上頑張った生徒は平均点を超えられていない
つまり、スマホの使用時間が長くなるほど、学力の低下を招いている可能性が十分に考えられるということがわかります。
では、スマホの使用は学力ばかりに影響するのでしょうか? それ以上に大きな代償があるとも言われています。
スマホ・テレビ・ゲームが脳に与える影響
●前頭前野の働きが抑えられる
前頭前野は、「考える力」「人の気持ちを理解する力」「感情のコントロール」「計画性」などをつかさどる重要な部分で、中学生の時期に急速に発達することが知られています。しかし、スマホを長時間使うとこの前頭前野の働きが鈍くなり、集中力や自己コントロール力が低下するという研究結果が出ています。
- SNSや動画視聴中、前頭前野の血流が低下する
- 慣れれば慣れるほど、脳が刺激に鈍感になり、深く考える力が落ちる
これは、学力の土台となる力が育ちにくくなることを意味します。
●報酬系の過剰刺激と依存のリスク
スマホやゲームは、通知・「いいね」・スコアなどで、脳の報酬系(ドーパミン回路)を強く刺激します。特に中学生は、前頭前野による「がまんする力」がまだ未熟なため、依存しやすい傾向があります。
MRIによる研究では、スマホやゲームに依存した脳は、報酬系が過剰に反応し、逆に前頭前野の活動が低下していることが確認されています。

(出典元 https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101101/)
●使用を制限すれば、学力も回復できる
希望のある事実として、スマホの使用を制限することで、脳の働きも学力も回復することが分かっています。
文科省の追跡調査では、スマホの使用を1日1時間未満にした生徒が、偏差値を数ヶ月で回復させた事例が多数報告されています。使用をやめた時間を読書・睡眠・運動にあてたことで、集中力や思考力が戻ったと本人も実感している例が多くあります。
スマホとの付き合い方~今日からできる工夫~
スマホを完全に禁止する必要はありません。大切なのは、「どう使うか」です。
生徒向けアドバイス
- 使用時間は1日1時間以内を目安に
- 勉強中や就寝前は、手の届かない場所に置く
- SNSや動画は「何となく」ではなく、見る時間・目的を決めて使う
- スマホの代わりに、手を動かす趣味や、運動・読書の時間を取り入れる
保護者向けアドバイス
- 使用ルールは「一緒に決める」ことで納得感を持たせる
- 勉強中・食事中・就寝前など、使わない時間帯を明確にする
- 保護者自身もスマホの使い方を見せ、お手本となる行動を
- 「ダメ!」ではなく、目的を持った使い方を一緒に考える姿勢が大切
まとめ
スマホは便利な道具であり、正しく使えば生活を豊かにするものです。しかし、使い方を誤ると、学力や脳の発達に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
今、脳が大きく育つ中学生の時期には、「スマホとの賢いつき合い方」を身につけ、今日からできる工夫を少しずつ取り入れて、勉強も心も健康に育てていきましょう。
【お問い合わせ・無料体験授業のお申込み】
TEL: 0144-82-8011
公式LINEでのお問い合わせも大歓迎です!


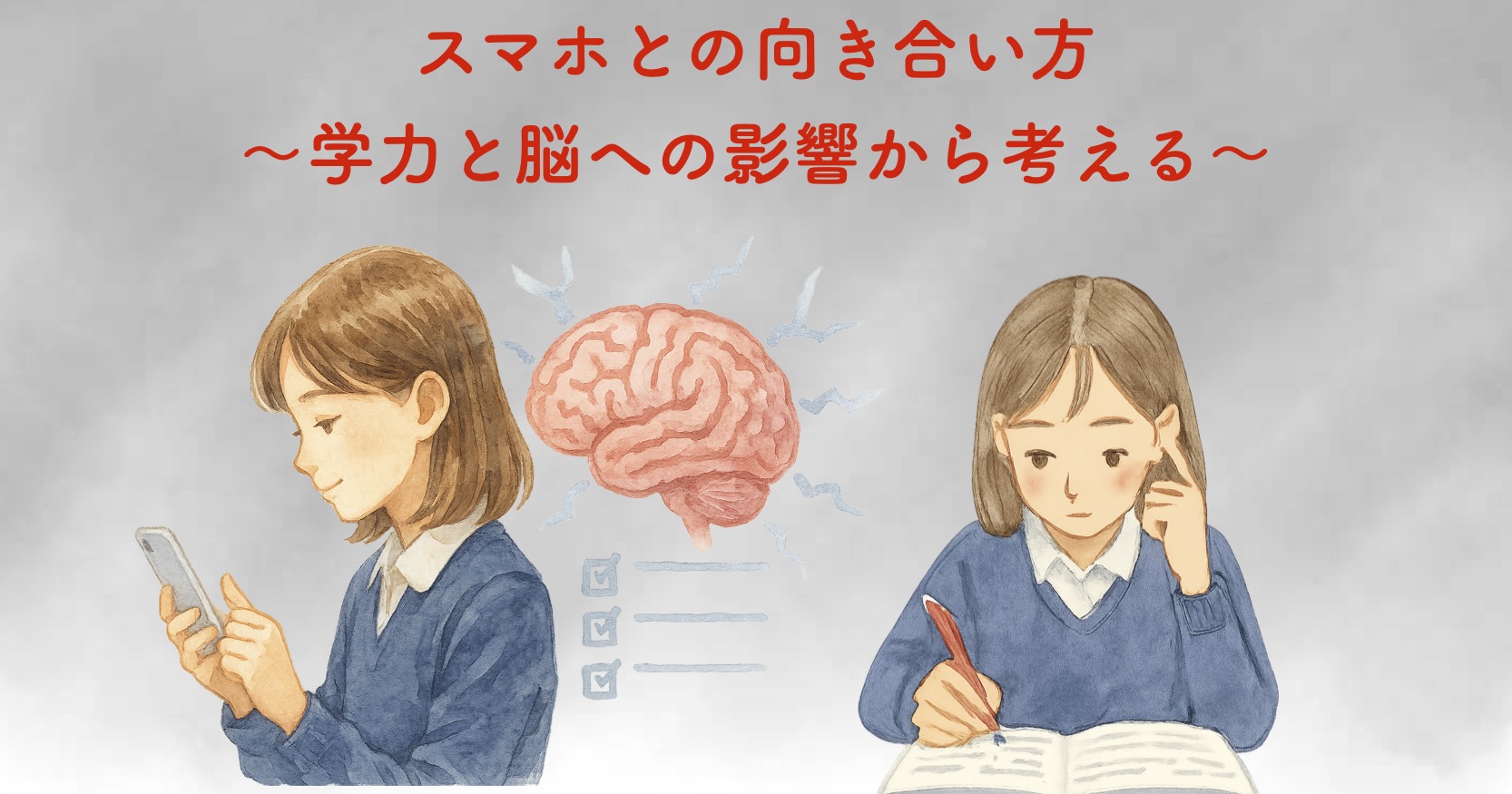
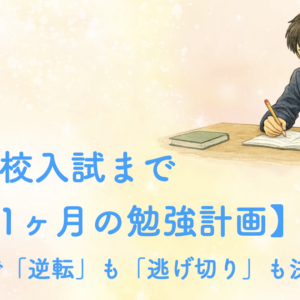
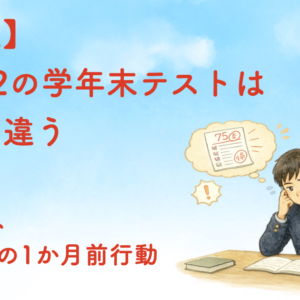
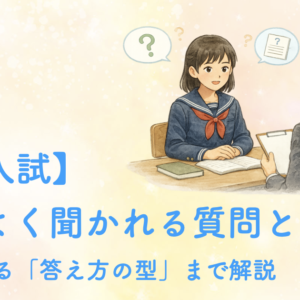
コメント